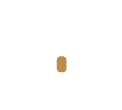寿司桶でつくるおもてなし料理
寿司桶レシピ
おうち時間には家族で寿司桶を使った五目ちらし寿司♪
五目ちらし寿司とは、酢飯の上に、干しシイタケの煮物、錦糸卵、酢れんこん、刻みのりなどの味のベースになるものと、季節の彩りを魅せる海老やいくら、ゆでた絹さやなどを載せたお寿司です。
実は作り置きをしておけば、作る当日はとてもカンタンに調理ができるので、
おうちで退屈しているお子さんも一緒に、
ぜひ寿司桶を使ったちらし寿司にチャレンジしてみてください♪
子どものお手伝いポイント
- うちわでパタパタとあおい寿司飯を冷ます
- 具材のトッピング
<事前に用意できるもの>
「干しシイタケの煮物」—冷蔵庫で1週間
「酢れんこん」—冷蔵庫で1週間
「錦糸卵」—冷蔵で1日
作り方はこちらから https://shimizumokuzai.jp/sushirecipe/8923.html
【当日のつくりかた】
寿司桶(飯台)は水で濡らしたあと、水気を拭き取っておきます。
<予め作っておいた具材>
・干しシイタケの煮物
半量を取り出し、細かく切り刻んだものを、酢飯に混ぜ合わるようにとっておきます。
残りは飾り用に短冊切りにします。
・酢れんこん
汁気をしっかり切っておきます。
・錦糸卵
使いやすいようにお皿にうつしておきましょう。
<ごはん>
米 3合
昆布 5センチ角1枚
水 白米に適した量
洗った白米に3合の線まで水を入れ、乾燥昆布を入れてスイッチオンします。
炊きあがったら、昆布は捨てて、寿司桶へと移します。
<寿司飯>
炊きあがったごはん 3合
☆酢 大さじ4
☆砂糖 大さじ4
☆塩 小さじ1.5
干しシイタケの煮物(細かく切り刻んだもの)
☆酢、☆砂糖、☆塩をボウルに入れて砂糖が溶けるまでよく混ぜ合わせます。
寿司桶に入ったごはんを切るように混ぜながら☆のあわせ酢を振りかけていきます。
底の部分が熱いままにならないように、上下を大きく返します。全体が寿司酢をまとってつややかに輝くまで手早く合わせます。
ごはんとあわせ酢がなじんだら、すし飯を広げてうちあわでパタパタとあおいで冷まします。表面のあら熱が取れたら、しゃもじで上下を返しながら、全体が人肌の温度くらいになるまで冷まします。
最後に欲しシイタケの煮物を混ぜます。
できたら乾かないように、濡れ布巾をかぶせておきます。常温で置いておきます。
<当日用意する彩りの具材>
えび 適量
きぬさや 適量
いくら 適量
きざみ海苔 適量
桜でんぶ お好みで
えびは殻付きのままで背ワタをとって、
酒と塩(分量外)を入れたお湯で塩ゆでします。
茹で上がったら殻を取り除いて、キッチンペーパーで水気をとっておきます。
きぬさやも茹でて、半分にカットし、水気をキッチンペーパーでとっておきましょう。
<盛り付け>
寿司桶の中にそのまま飾っても良いですし、一人分ずつ器に盛っても良いですね。
寿司桶でも、お皿でも、盛り付けの基本は同じです。
はじめに寿司飯、つぎにきざみ海苔と錦糸卵を広げます。
次に彩りにはあまり関係のない酢れんこんやシイタケをのせ、続けてきぬさやをのせます。
次に彩のよいイクラやゆでた海老などをのせていき、お好みで「桜でんぶ」を載せます。甘くなるのでちらし寿司が苦手なお子さんも食べやすくなりますよ。
大きな具材から小さい具材へと順番に盛り付けていく感じですね。
上から見て、全体的にまんべんなく具材が散らばっていて、取り分けしやすくなっていれば完成です♪
【寿司桶を選ぶコツ】
寿司桶は、ごはんを入れるだけじゃなく、酢飯をつくったり、具材を盛ったりするのに活躍する調理器具です。
なので、少し大きめの方が重宝します♪
例えばこちら、4人用という形で、お米は3合となっています。
志水木材産業では、寿司桶に「お米を入れたときにの目安の図」が載っていますのでそちらも参考に大き目なものを選ぶと良いですよ。
https://shimizumokuzai.jp/goods/7453.html
寿司桶の通販はこちらから
https://shimizumokuzai.jp/goods_cat/sushioke_all
寿司桶がちょっと傷んできてしまったという方は
こちらの寿司桶のお手入れをお読みください
寿司桶の修理はこちらから

この記事が気に入ったら
いいね!してね!