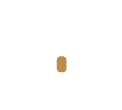寿司桶でつくるおもてなし料理
寿司桶レシピ
刺身が映える!盛り桶としても使える寿司桶。
1家に1台はおいておきたい調理道具として、
酢飯をつくるときに重宝する寿司桶は外せません。
沢山のごはんを、上手に水分調整しながら混ぜられる寿司桶は、
お母さんが使っていたものをそのまま娘さんが受け継いで使い続けたりと、
ずっと使える調理器具としても人気があります。
出番の少ない「寿司桶」をもっと使いたい!
寿司桶は、みなさんのお家では、どのくらいの頻度で食卓に登場していますか?
1ヵ月に1回程度、年に数回程度、という方がほとんどではないでしょうか。
寿司桶は、酢飯をつくるときのみに使うのだけでは勿体ない!
木のもつ素朴感と存在感をあわせもつ寿司桶は、
盛り桶として使えば、いつものごはんをもっと華やかに演出してくれます。
例えば、スーパーで買ってきた刺身を盛りつけるときに、
お皿ではなく、この寿司桶を使うことで、
まるで居酒屋さんで出てきた刺身盛りのように華やかに変身するんです。
お刺身を上手に盛るコツ
- 皿の奥にはツマと青じそを盛る。
皿の奥川に置くツマは大き目に、青じそは正面から見て斜めになるように置くと良いでしょう。
高低差をつけて、奥から順番に盛り付けていきます。 - 刺身をツマによりかかせるように立たせるように置きます。
- 刺身は2~3枚ずつ、角度をそろえてずらして置きます。
- 手前にもツマ(小盛り)と青じそをしいて刺身を置く。
- 空いているスペースにわさび、たんぽぽ、赤芽などを添えて仕上げます。
野菜盛りにも寿司桶で一際おいしく魅せる!
ナチュラルな自然の色を持つ寿司桶は、自然の素材がよく似合います。
氷と野菜をいれてディスプレイすれば素敵な野菜盛りが完成!
この野菜盛りのコツは、お刺身盛りとそれほど変わりません。
奥は背を高く、手前は低くすることで、バランスよく飾れます。
また、氷とラムネを入れたり、スイカを冷やすのにもオススメ。
ビールなんかも一緒に冷やしたら日本ならではの風情が溢れますね。
川辺でBBQの時などにはぜひ活用したいもの。
食器を洗ったりり片づけたりなどのときにも使えてとっても便利ですよ。
オススメの寿司桶は?
寿司桶といっても、様々な種類があります。
その中でも、オススメの寿司桶を見極めるコツをお教えいたします。
寿司桶に使用される木材には、桧(ひのき)やモミ、松などがありますが、その中でおすすめのが「椹(さわら)」なんです。
特に「木曽さわら」を使用した寿司桶が、特に質が高い逸品として人気があります。
その理由として、さわらの持つ高い調湿作用が挙げられます。
水分の調節が簡単に行え、仕上がりのごはんはツヤツヤとしており、ちょうど良い硬さの酢飯となるからです。
木の香りも高く、ふんわりと風味がよくなり、よりおいしい酢飯を作ることができます。
また、使う木材の部位によっても寿司桶となった後の耐水性や耐久性に差が生じます。
心材(赤身材)は木の中心部にあります。ここは木が最も成熟した部分で、耐水性に優れ、菌にも強く耐久性が高くなります。
そのまわりの辺材は白太(しらた)と呼ばれ、タンパク質が多いためカビやすく、赤身材と比べて耐水性、耐久性に劣ります。
そして木の挽き方でもその木材に違いがあります。
丸太の中心付近を製材した「柾目(まさめ)材」は木の収縮が少なく、寿司桶に最適です。
外側を製材した「板目(いため)材」は、若くて柔らかいため、歳月が経つにつれて、柾目材よりも反りや狂いが生じやすくなるため、寿司桶には向いていません。
逆に板目材は木の表情が出やすいため、床材や家具材として人気がありますね。
このポイントをまとめると耐水性に優れていることで耐久性がよく、調湿作用が高い寿司桶は、「木曽椹(さわら)の赤身の柾目材の寿司桶」となります。
志水木材産業の寿司桶はすべて木曽椹(さわら)の赤身の柾目材です。
安心してお選びいただけますね。
夏にもピッタリの寿司桶活用方法いかがでしたか。
使用の前に軽く濡れたフキンで拭いてからご使用いただくと、
食品の匂いや色が染みこみにくくなり、黒ずみも防げます。
またご使用後は、水、またはお湯で洗い、水気を拭き取り乾かしてください。
洗剤を使用する場合は、台所用中性洗剤をお使いください。
ぜひお家でも寿司桶をいろいろなシーンでご活用くださいね。

この記事が気に入ったら
いいね!してね!