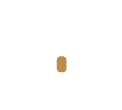寿司桶でつくるおもてなし料理
寿司桶レシピ
どれを選べばいい?わかりやすい寿司桶の選び方と使い方
ちらし寿司や手巻き寿司、お祝いの席に欠かせない寿司桶(すしおけ)。
でも「どれを選んだらいいの?」「木の種類によって違いはあるの?」と、初めてだと迷ってしまいますよね。
今回は、そんな方に向けて、寿司桶の基本的な知識から選ぶときのポイントまで、わかりやすくご紹介します。
これを読めば、自分にぴったりの寿司桶がきっと見つかりますよ。
寿司桶ってどんな道具?
寿司桶は、ごはんに酢を混ぜて「酢飯」をつくるための木の桶です。

日本では昔から、ちらし寿司や巻き寿司、握り寿司などの調理に使われてきました。
酢飯を混ぜるときに、ごはんの熱と余分な水分を適度に逃がしてくれるのが木製寿司桶の大きな特徴。
おいしくふっくらとした酢飯が仕上がります。
寿司桶の「サイズ」の選び方
サイズ選びの目安は、「何合のごはんを炊くか」で決まります。
| ごはんの量 | 寿司桶のサイズ(目安) | 目安の人数 |
| 2合まで | 約24cm | 1~2人前 |
| 3~5合 | 約27~30cm | 3~5人前 |
| 6合以上 | 33cm以上 | 6人以上~ |
※人数はちらし寿司や手巻き寿司で食べる場合の目安です。 「ちょっと大きめかな?」と思うくらいが混ぜやすくておすすめですよ。
素材で変わる風味と使い心地
寿司桶に使われる木材は、主に「杉(すぎ)」と「椹(さわら)」です。それぞれの特徴はこちらです。
杉(すぎ)
- ・木目が美しく、香りもやさしい
- ・吸水性が高く、酢飯がベタつきにくい
- ・軽くて扱いやすい
- ・秋田杉や吉野杉など、産地によって風合いも異なる
椹(さわら)
- ・ヒノキ科の針葉樹で、水や湿気に強く、耐久性が高い
- ・杉に比べて木目がやや緻密で、反りや割れが起きにくい
- ・軽くて加工しやすく、表面もなめらか
- ・香りは控えめで上品、酢飯の香りを邪魔しにくい
- ・水切れがよく、清潔感を保ちやすい
どちらもごはんをおいしく仕上げるにはぴったりの木材ですが、軽さや風合いで選ぶなら杉、丈夫さと香りで選ぶならさわらがおすすめです。
「形」や「仕様」にも注目
寿司桶は丸い「円形」が定番ですが、以前は四角いタイプのものもありました。
- ・円形タイプ:混ぜやすく、見た目もきれい。伝統的な形。

- ・フタ付きタイプ:保存にも便利。ラップを使わなくても乾燥を防げます。

- ・取っ手付きタイプ:持ち運びがラク。行楽弁当や持ち寄りに◎
日常的に使いたい方は、「フタ付き・軽量タイプ」など実用性もチェックしてみましょう。
お手入れ方法と長持ちのコツ
寿司桶は天然木製のものが多いため、ちょっとしたお手入れで長く使えます。
使用前:
- ・さっと水でぬらしてから使うと、ごはんがくっつきにくくなります。
使用後:
- ・中性洗剤はなるべく使わず、ぬるま湯と柔らかいスポンジで洗う
- ・しっかり乾かしてから風通しのよい場所に保管
- ・直射日光は避けること!
カビ防止のためにも、使った後の乾燥がいちばん大切です。
まとめ:自分に合った寿司桶を選んで、寿司づくりをもっと楽しく!
寿司桶は、見た目の美しさだけでなく、酢飯をおいしく仕上げるための大切な道具です。
「家族で手巻き寿司を楽しみたい」「行事のたびにちらし寿司を作りたい」 そんな暮らしの中に、お気に入りの寿司桶があれば、食卓がもっと豊かになりますよ。
ぜひ、サイズ・素材・形の違いを知ったうえで、自分にぴったりの一本を選んでみてくださいね。

この記事が気に入ったら
いいね!してね!